

大学受験に向けて、多くの高校では高1生の後半で文系コース、理系コースのどちらに進むかを選ぶ文理選択があります。文系か理系かの選択は、大学受験だけでなく、大学で専門的に学ぶ学問、またその先の就職や社会人生活に大きく影響します。自分が将来進む道を決める大切な選択であることを理解して、文系・理系を選びましょう。 この記事では文理選択に悩む高校生に向けて、文系と理系の違いや選ぶポイントをお伝えします。

まず、文系と理系の違いや基本情報について見ていきましょう。
代表的な文系の学問、理系の学部の一例をご紹介します。

文系学部と理系学部では、大学生活のスタイルにも違いがあります。大学にもよりますが、一般的な内容をご紹介します。
文系
・2年又は3年生からゼミが始まり、基本は週1回、理系と比較して拘束時間は短め
・自由に使える時間が比較的多く、サークル活動やアルバイトなどに力を入れている人も多い
理系
・実験が多い
・課題や実験レポートの提出が多い
・3年生から研究室に所属し、4年生からは研究室中心の生活になる
・文系ほどではないがサークル活動やアルバイトもできる
文系は業界問わず総合職や営業、事務など、理系は大学で学んだ専門分野を活かした業界、職種に就く傾向にあります。

※上記はあくまでも一例です。また文系でも理系の職種、理系でも文系の職種に就く場合もあります。
国立教育政策研究所の調査結果では、高3生で理系を選択する生徒の割合が32%、文系を選択する生徒は68%と、圧倒的に文系の割合が高くなっています。
出典:文部科学省ホームページ 初等中等教育分科会(第122回) 配付資料
(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/1416449.htm)
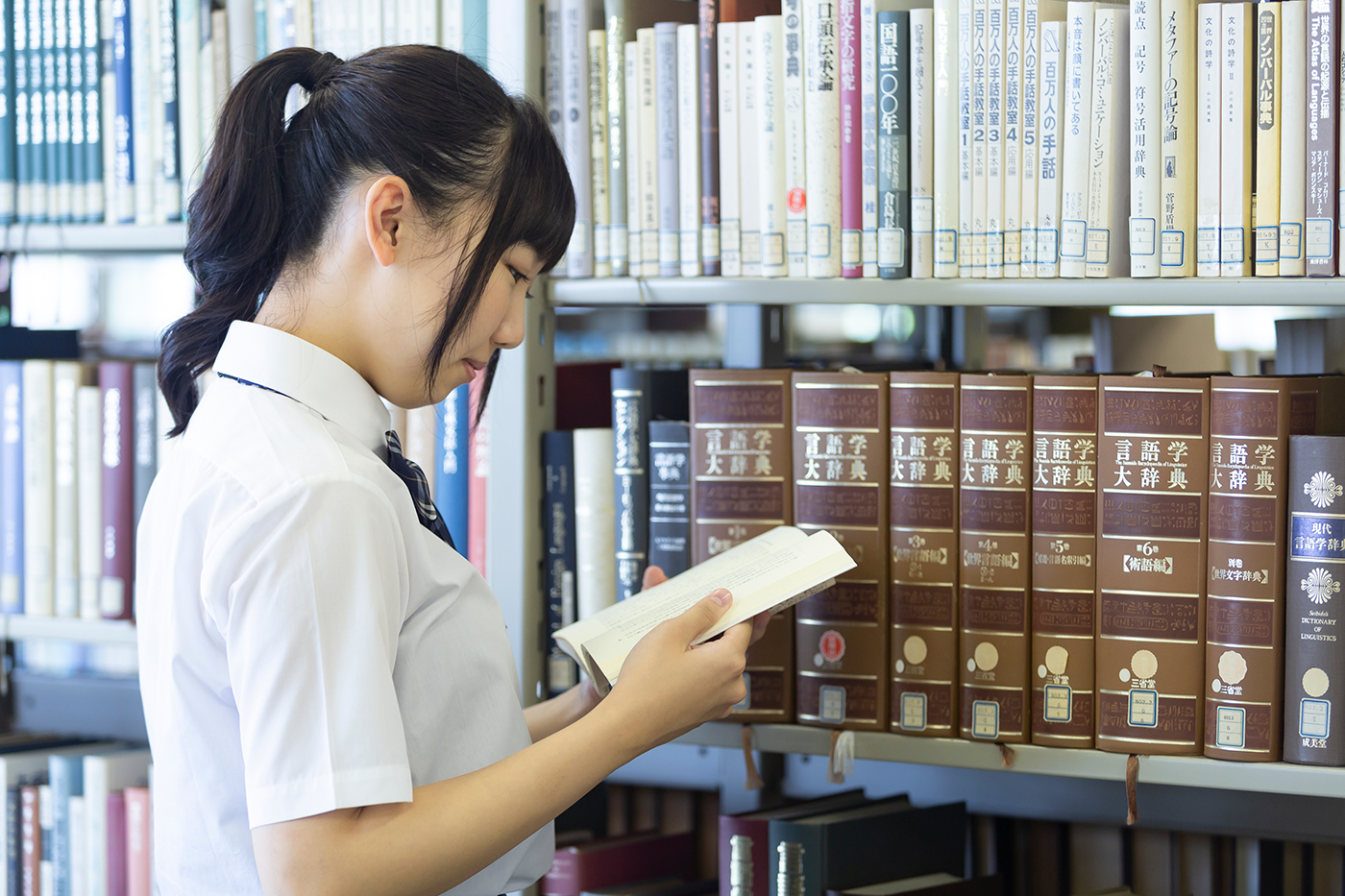
文系と理系の違いを理解したところで、文系と理系をどう選べばよいかのポイントを見ていきましょう。
勉強していてワクワクする教科や、学んでみたい分野があれば、それに該当する学問が文系か理系かで選びましょう。
特に思い浮かばない人は、勉強以外で興味のあることを書き出してみましょう。
例えば本を読むのが好きなら文学、ボランティアに興味があるなら社会福祉学、機械の仕組みやものづくりが好きなら工学……などです。
最初にご紹介したように、文系か理系かの選択は、将来の職業にも直結します。
理系では医師や薬剤師、文系では弁護士などの法曹関係などの職業に就くには資格が必要で、おのずと進むべき学部が決まります。また資格が不要でも、研究職や技術職は専門的な知識や考え方が必要となり、理系の学部で学ぶ必要があります。
就きたい職業が決まっていない人も、どんな仕事なら楽しくできそうかを想像しながら就きたい職業を考えてみましょう。自分のやりたい仕事から、何を学べばよいかが分かってくるはずです。
興味のあることや学んでみたいこと、将来やりたい仕事から、具体的にどの大学のどの学部でそれが学べるのかを調べ、志望校を決めます。
受験に必要な科目を調べたら、高校ではそれを履修できるコース(文系または理系コース)を選びましょう。

「数学が苦手だから文系を選ぶ」というような理由で文理選択しようとしていませんか?自分が将来進みたい道にも関わってくる事もあるため、科目の得意・不得意だけで文系・理系を決めるのはおすすめしません。
2018年ごろからの流れとして、私立難関大学の文系学部でも受験科目に数学を必須とする大学が増えてきています。国公立大を目指す場合、文系でも共通テストでは数学が課される場合がほとんどです。経済学部や経営学部などは大学に入ってからも数学は必須です。
同じように、理系であっても英語は必須。大学入学後も英語の書物や論文を読むなど、英語が必要な場面はたくさんあります。
もともと不得意な科目を得意にするのはなかなか難しいかもしれませんが、苦手だからと避けるのではなく、文系科目・理系科目ともにある程度は得点できるようにしておくことが大切です。
文理選択は自分が将来進みたい道、どんな社会人生活をしたいかをじっくり考えた上で決めることをおすすめします。
科目の得意・不得意だけで決めてしまうと、受験勉強の途中でモチベーションが保てなくなることも。将来を考えることで、自分が何を学ぶべきかが見えてきて、受験勉強へのモチベーションも上がるはずです。
志望校合格、またその先の将来の目標を見据えれば、苦手な教科にも少しずつ取り組んでいくことができるでしょう。
受験がゴールではない!文理選択は将来の自分を作る大切な選択
文理選択のポイントについて解説してきました。文系・理系の選択は大学卒業後の職業に直結する大切な選択です。興味のあることや学びたいこと、将来就きたい職業などから逆算して選びましょう。
大学受験はあくまで通過点。高校時点での科目の得意・不得意だけで文理選択するのではなく、大学生になった自分、社会人になった自分を想像しながら、進みたい大学・学部を選びましょう。
Photo / Getty Images